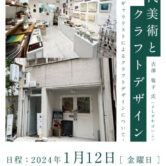

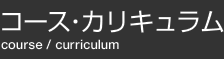
![]()
器、家具、照明器具など日常生活の中で使う工芸品には、実用性と、使ってこその美しさが求められます。
これらのモノと人、暮らしとの結びつきを深く考えながら、クレイワーク(陶芸)、ウッドワーク(木工)のすべてを体験。さまざまな素材の質感、色彩、耐性といった基礎知識と、造形のプロセスを学びます。



※教職課程の所定科目単位の習得が必要です。
建築・環境デザイン学科 吉田 淳一 教授
クラフトデザインは、芸術的創造の基礎として手工業(クラフト)へ回帰することで、芸術と生産の分離状態から脱して、造形活動によって現代の人間社会にふさわしい美的造形と空間を創造することを目的としている。また、「美と用の調和」という対比や対極の概念を押さえるということは、事物や現象を全体として捉えていくこととなり、造形デザインにおいて、形態全体の有機的なつながりを求めることは重要なことである。造形制作に係わる技術の習得と素材体験に基づく具体的なデザインの発想は、対極である「美と用」の二極性をはらんではいるが、現在に至るまで抱えてきた問題であり、美術とa工芸という分野の総合が求められている。そのことは、造形作品を、一人の人間が発想から制作までの全工程を行うことで、全体性を見つめることにつながり、解決の糸口となる。このように、作る側には、諸感覚における総合的な人間が求められ、造形デザインを行う過程にあっても、様々な要素の対比と調和が要求される。
総合的視野でデザインを考えられる、総合的なタイプの造形作家(デザイナー)の養成という目標にとって、不可欠な実践的かつ理論的な専門知識と共に特に学ぶべきことは、形態には何ら自明のものがないという自覚、および、何か本当に新しいものを創造する場合の前提である。すなわち、予め造形(デザイン)の諸問題に対して可能な限り多くの要因と取り組み、物事をあたかも初めてのようにじっくり観察する状態になりうることで、それに基づくスケッチのプロセスをできるだけ基本的な現象と過程に還元することが望まれる。
素材別にクラフトデザインを見てみると、クレイワーク(陶芸)、メタルワーク(金工)、ウッドワーク(木工)、ファイバーワーク(染織)、グラスワーク(ガラス)などがある。
次に、個々の造形デザインの特性と制作技術による表現の可能性について、述べることとする。
クレイワークとは、粘土を使って造形した作品であり、高温の窯で焼成することで、陶磁器は完成する。
造形方法には、ろくろを回して皿や壺などの形を作っていく方法や、手びねりの方法、或いは型を用いて粘土を成形する方法などがある。
焼き方にも、窯を用いない「野焼き」などもあり、土の種類やこね方、施釉、焼成温度など、様々な要素が作品の成立に係わってくる。したがって、いろいろな技法と造形が存在することとなる。
粘土という可塑性のある素材は、最も取っ付きやすいものではあるが、器の制作だけではない多様性のある、造形表現に多くの可能性を持った素材と言える。生活に身近な食器から、外部空間におけるタイル陶板のデザインやモニュメントとしての環境造形まで、幅広く対応できる。また、素材の特徴を生かした現代美術造形としての「オブジェ陶器」を生み出すこととなった。
ウッドワークとは、木材を加工して造形された作品であるが、ここでは、角材、板材に加工された木材を切断し、研磨したりして出来上がるものを指す。
木工は、木の特性を生かしたテーブルウェアーとしての箸を含むスプーンなどのカトラリーのデザインから、木製玩具、木製家具デザインまでと、インテリアないしプロダクトデザインの領域にまで及ぶ幅広い造形表現を持っている。
現在では、帯ノコ、ルーター、サンダーなどの電動工具を用いて、切断、研磨をおこなうことが多いので作業が容易になったが、図面や縮尺模型などを用いてデザインをチェックし、計画性をもって望まないと、魅力ある造形作品を生み出す結果にはつながらない。
また、木製家具をはじめとした木製品は、表面の塗装が必要となり、ニス、ラッカー、漆などの塗料の選別と塗装仕上げが完成の出来栄えを左右する。